耽美試行
花舞-5-
21〜25 2016.7.19〜2016.8.16
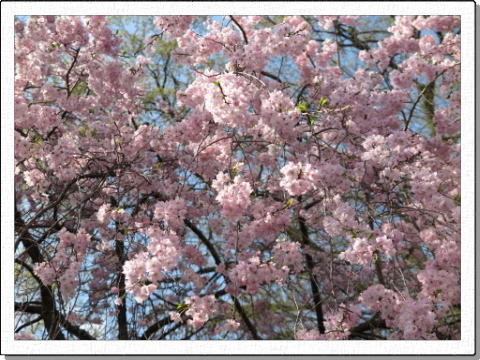
5-1-
美佐子は25歳を越えてしまって、大学の友達がぼちぼち結婚式をあげる、という知らせを受けるようになっています。親友だった大島佳織が結婚式を挙げるから、式と披露宴に出席してほしいとの案内をもらって、うらやましい気持ちにもなったけれど、当然、出席すると返事を出しました。その結婚式が、今日、パレスサイドホテルで行われるというので、洋装で出席するのです。仲の良かった友達が集まるから、臨時の同窓会の感もあり、知らないところへ行くというより、行きなれたところへ行く感覚のほうが強い。
「ええ、向井美佐子、ここです、ここにあります」
「ああ、向井さん、ありがとうございます」
受付をしている女子は、美佐子の知らない子で、銀行勤めをしている大島佳織だから、その同僚なのかも知れない。なにより相手とは務める銀行の先輩男子で職場結婚です。
「式に出席いただいて、記念写真していただいて、それから披露宴は」
「午後二時半からでしたよね、披露宴」
「なんだぁ、麻里も来てるんだ、久しぶりぃ」
受付で手続きをしていると、うしろから近づいてきたのが白井麻里。大学時代の親友だけど、卒業して四年が過ぎて、最近はご無沙汰気味になっている女子です。
「いることはいるけど、まだ、決めていないよ」
「そうなの、わたしは、来年、まだ半年以上先だけど、結婚する予定」
「決まってるんだ、麻里ちゃん、それはおめでとう」
「それより佳織、もう、できちゃってるんだって」
「ええっ、そうなの、だから、突然という感じなんだ」
「美佐ちゃんは、もう、してるんでしょ」
「なによぉ、麻里ちゃんは、どうなの、幸せ?」
「まぁね、彼は、逞しいほうだと思う、たぶん」
「お金、いるんでしょ、一式するとなると」
「うん、わたしたちは、お金をかけない、もったいないから」
「それもそうね、麻里のは、職場結婚だから、本式だよね」
「二百万とか三百万とか、かけてるんかなぁ」
「麻里のお父さんは、会社の経営者だから、いいんじゃない」
結婚式がはじまるまえの時間、美佐子は久しぶりに会った白井麻里と、結婚についての情報交換をしているんです。年頃、25歳を越えた女子の関心ごとといえば、現実味を帯びている結婚のことです。美佐子の場合、相手は由岐康夫28歳、由岐織物の経営を引き継ぐ御曹司です。康夫とはもう一緒に棲んでもいい関係になっているところだけど、結婚に至るには、京都の老舗織物会社の御曹司、まだまだ難題があるところなのです。
5-2-
結婚式はホテルの中に造られた教会スペースで執り行われ、記念写真を撮った後、披露宴へとつながっていきます。参列者たちは、それぞれにお祝いの気持ちと、独身者には羨ましさ、既婚者においても羨望の目線で臨まれています。
「新婚っていったって、すぐに子供ができちゃうんだよね」
「そうなのよね、おおっぴらに楽しむどころじゃないかも」
「そうよね、ところで、美佐子はどうなの、満足してるの?」
「なにが、なにに、満足してるって、ゆうのよぉ」
「ふふん、彼とのことよ、してるんでしょ」
「麻里みたいに、婚約してないのよ、でもさ」
「でも、してるんでしょ、子供、つくっちゃだめよ」
披露の開宴を待つ時間、被災ぶりに会った麻里と、意味深な会話を交わす美佐子です。そんなはなし、だれにできるというわけでもなく、内緒の内緒、誰にもいえなくて、そうしたものかと思い悩むこともある美佐子でした。
美佐子の恋人由岐康夫は、老舗の織物会社で家業の後を継ぐ立場です。28歳、大学を出て、気ままに過ごしてきたお坊ちゃまとでもいえばいい立場です。美佐子の相手としては、申し分ない人物ですが、康夫の親からは、美佐子の家の品格が、釣り合わないと思われていることです。今の時代に、家柄とか風格とか、そういった事情は、ふたりの気持ちには無縁のもの、とばかりも言っていられないのが実情です。
「そうよ、シュールな、アンティークなお店を、やるかも」
「どこで、だれと、するのよぉ」
麻里には、康夫の計画話を伝えてもいいかと思って、美佐子は、まだ本決まりではない古書店の話を、打ち明けるのでした。
「京都で、マンションのワンフロアー、五千万円ならなんとかなるんだって」
「それで、足りるの?、そんな話、ほんとうなの?」
「まあ、いまは、彼の、趣味、だというけど、もう場所も、決まってる」
美佐子は、まだ実感がわいてこないけれど、このまえには物件を見に行ったこともあって、決して他人事ではなく、不安だらけだけど、そこにいる自分の姿を、想像してみたりするところでした。
5-3-
「そうなのよね、相手の家柄とか、織物会社の息子なのよ」
「それで、跡継ぎの嫁に、美佐子を、ということなんでしょ」
「そうなんだけど、どうもわたしでは不足みないなのよ」
「なんなのよ、そんなこと、結婚って、本人どうしじゃないの」
「まあまあ、若奥様、わたし、べつに、共働きでもいいんだけど」
美佐子の身の上相談というより、話題にして、美佐子は楽しむ。麻里は婚約している身だから、話題にできる。
「麻里は、どうなの」
「うんうん、わたしの相手は、商社マン、なのよ」
「そうなの、当面、共働き、子供ができたら専業主婦、なの?」
「たぶん、そうなる、わたし、絵を描き続けたいから」
「そうなのね、そうしなさいよ、麻里は芸術家、だから」
美佐子は、といえば優秀なる特技があるわけでもなく、結婚できても成り行き任せなところもあります。シュールリアリズム系の書籍などを扱う書店を経営する、とはいっても美佐子には経営する才覚があるとは思っていないが、けっこう楽しそうな企画ができそうだと思えるところです。
結婚式の披露宴で、友達としてスピーチを頼まれていた美佐子。祝福ムードに満ちた披露宴にふさわしい、お祝いの言葉、祝辞、一分間スピーチです。
「おめでとうございます、佳織とは、大学時代の友だちです」
「旦那様を大切にして、いい家庭を築いてくださいね」
ありきたりの、お定まりの、スピーチ。美佐子は、予定調和的な出来事に、違和感は抱かないけど、なにかしら物足りない気がして仕方がないのです。
<妊娠かぁ、佳織、できちゃったんだよね>
<わたしのばあい、どうなんだろ、気をつけなくっちゃ>
由岐康夫のことを想いつつ、披露宴の席では、妊娠している佳織の顔を見つつ、結果として、こうして結ばれたことを、祝福する気持ちです。同棲するところにまでも発展していない康夫との関係です。佳織のようなケースになったとき、どうのようなことになるのだろうか、と心配になってきます。なるようになるなんていう友だちもいるけど、なるようにはならない、と思ってしまう性格の美佐子でもあるのです。
5-4-
結婚式の披露宴は、晴れがましいけれど、女子にとってはうれしい。生きてきた中での最大の祝福すべきイベント。向井美佐子は25歳を過ぎて、現実のこととしてイメージできるようになっています。
<いくらお金がかかってたんやろ、わたしにも、できるかなぁ>
妊娠してしまったから、結婚式を挙げる、というのもなんだか変なセレモニーのように思えてしまう美佐子ですが、結婚式を否定するつもりは全くありません。
<由岐さんと、結婚式して、家庭をつくる、そうゆううことだよね>
こころのなかで呟く美佐子。ワンルームの自分の居場所へ戻ってきて、そこには由岐康夫は居なくて、自分ひとりだけであることを確認します。
<このベッド、ああ、いっしょにいるんだ、康夫と一緒にすごす・・・・>
結婚式と披露宴に出て、帰ってきて、気持ちは疲れているけど、頭は冴えていて、興奮してるのか。美佐子の内面には、できちゃった婚だといっても、幸せな振る舞いだった友達の姿が焼き付いていて、思い起こすんです。普段着どころかショーツだけの格好になった美佐子は、目の前にあるシングルの白ベッドを眺めます。そうして、シーツに手を置いて、撫ぜ、枕を撫ぜ、ため息のような小声を洩らしてしまいます。
<うううん、ちゃうの、わたし、ちゃうの、ちゃう、ちゃうぅ>
立ったまま、ベッドの頭に左手置いて、右手をショーツのなかへ入れてしまった美佐子。
<由岐さん、康夫さん、どうしたの、結婚しない、できない、どうして>
右手の指で、恥丘の下部をまさぐりだして、ため息を洩らしながら、からだへ刺激を与えていく美佐子。
「はぁあ、ああっ、ああああっ」
六畳のワンルーム、誰もいない、自分だけ。自分の部屋。自分を飾るモノたちが、部屋の中、所狭しと置いてある。洗濯し、干してあるインナーの、丸いハンガー。小さな書棚には、由岐からもらったシュールリアリズム宣言という本。芥川賞をもらったという単行本。小型の冷蔵冷凍庫。レトルトの冷凍食品はあまり買わないけれど、チンだけで食べられるチャーハンとか。
「ああっ、はぁああ、あああっ」
右手の指先、敏感な個所を触ってしまう美佐子。ああ、いつごろから、こんなこと、してるんやろ、ああっ。気分が高じてきて、内面のというより身体への刺激で、性欲を処理してしまう適齢の女子。
「どうして、いやだぁ、わたし、はしたない、由岐さん、康夫さん、別れないわ、わたし」
終えたあと、空虚感といえばいいのか、満たされない方法で満たしてしまった嫌悪感にみまわれてしまう美佐子。
5-5-
ひとりで果てたあと、美佐子は風呂にはいります。六畳のワンルームについている風呂だから狭いです。風呂と便器は別にあるから、用をたしたあと入るのに不便は感じません。独り住まいのワンルーム。恋人の由岐康夫がやってきて、おえたあとにはふたりして風呂に入るのだけど、そのときはさすがに狭くって、抱きあうしかありません。
<疲れたなぁ、結婚式、披露宴、佳織はもっと疲れたのかしら、でも、いいなぁ>
<麻里はそのあとどうしたのかしら、彼と会ってるのかなぁ>
<お金が、いるんだよねぇ、わたしの貯金だけじゃ、足んないわ>
裸になって、風呂の湯につかりながら、美佐子の頭の中にいろいろと光景が浮かんできて、独り言をぶつぶつ。とはいっても、言葉になっているわけではないから、無言。頭が冴えて、次から次へとイメージが移っていきます。
<ばあちゃん、どうしてるんやろ、ながいこと、会ってないなぁ>
能登の海辺で暮らしている美佐子の祖母。もう八十に近い年齢ですが、美佐子がまだ実家にいたころには、ときあるごとに面倒をみてもらった記憶が、遠くの方からやってきます。由岐康夫のことは、まだ親にも、祖母にも話をしていないかれど、いずれ、親に話をすることになると思う美佐子です。
風呂上がりの素肌を、鏡に映している美佐子。六畳の間、シングルベッドの対面に姿見の縦長鏡を置いている美佐子です。裸のまま、小さな腰掛けに座って、鏡と向き合います。自撮りはしません。自分の裸の写真は撮っていません。鏡に映して、自分の肌を確認します。白いです。もう少し小麦色でもいいかと思うけれど、雪肌といえばいいのか、白い。太もも、腰、おなか、胸、乳房。乳房はそんなに大きくはないです。薄っぺらというのではないけれど、ぷっくらふくらんでいるけれど、垂れてはいません。
「ああっ、なんだろ、感じるぅ」
乳首をつまんでみると、敏感な細い刺激が、ツンツンとからだの内側へ滲みてきます。乳首の先に右手の中指、爪を立て、引っ掻いてみる。
「あっ、なんやろ、ああっ」
月の中で、いちばん敏感になっている日、なのかもしれないと美佐子は思う。からだが締まっている感じで、硬く閉ざしているようにも思えるのですが、触ってみると、敏感に反応してくるんです。
「だめよ、もう、さっき、しちゃったんだから、もう、だめ・・・・」
つぶやくように、ぶつぶつ、ひとりごとのなかで、からだの敏感な処を、刺激している美佐子です。